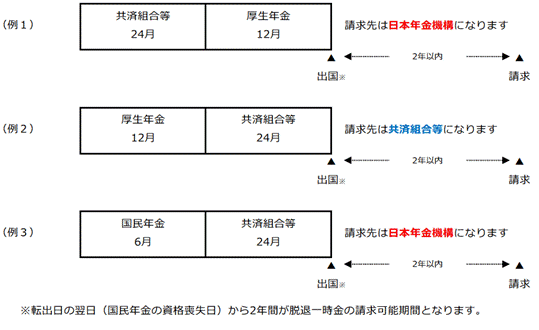- 老齢厚生年金の請求手続き
- 障害厚生年金の請求手続き
- 遺族厚生年金の請求手続
- 脱退一時金を受給するときの手続き
老齢厚生年金の請求手続き
支給開始年齢になったとき
- ■請求書の事前送付
- 受給開始年齢(注)に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3か月前から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きの案内を日本年金機構から本人あてに送付される。
- (注)受給開始年齢の詳細については こちらでご覧ください。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
- 支給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」が送付される。
その後65歳到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」およびリーフレット(「年金の請求手続きのご案内」)が日本年金機構から本人あてに送付される。
- ■請求書の提出について
- ・受給権発生日は支給開始齢に到達した日(誕生日の前日)となる。そのため、請求書の提出は支給開始年齢になってからの提出となる。支給開始年齢になる前に提出された場合は、受付されない。
- ・戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものを用意されたい。
- ※特別支給の老齢厚生年金の請求時において、加給年金額等の支給開始前の生計維持関係等の仮認定に必要な書類等に限っては、受給権発生日前に交付されたものであっても、提出日から6か月以内に交付されたものであれば、手続きが可能である。
- ※特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はないので、受給権発生日以降に速やかに請求されたい。
- ■年金請求書
- ・年金請求書は近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付てある。
・様式および記入例
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付 事前送付用)
- ※請求するときに必要な書類等については こちらでご覧ください。
特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続
65歳になったとき(厚生年金加入期間が1年未満の時)
- ■請求書の事前送付
- 60歳時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金保険の加入期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」が送付される。
その後65歳到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及びリーフレット(「年金の請求手続きのご案内」)を日本年金機構から本人あてに送付される。
なお、年金請求書は近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてある。
- ■請求書の提出について
- 受付は65歳になってからである。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものを用意されたい。
65歳になる前に提出された場合は受付されない。
- ●請求するときに必要な書類等
- ・年金請求書
年金請求書は近くの年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてある。
- ・様式および記入例
年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- ●請請求するときに必要な書類等についてはこちらでご覧ください。
65歳時の年金の手続き(厚生年金加入期間が1年未満の方)
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳になったとき
- 60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになる。この場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要である。
- ■届書の提出時期
- 65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」を送付されるので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ず提出されたい。届出が遅れると、年金の支払いが一時保留されることがあるので注意されたい。
- ■届書の提出先
- 〇提出先は日本年金機構本部へ提出。日本年金機構本部から送付された「年金請求書」のハガキを紛失された場合の届書は下記からダウンロードできます.
・国民年金・厚生年金保険 老齢給付年金請求書(加給年金対象額対象者有)
- ・国民年金・厚生年金保険 老齢給付年金請求書(加給年金対象額対象者無)
※加給年金額対象者の詳細についてはこちらでご覧ください
加給年金額
66歳以後に受給を繰下げたいとき
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金を65歳から受け取ることができる人が、65歳からではなく66歳以後に繰下げて受け取ることもできる。繰下げ請求をされた場合は、その申出月に応じた割合の額が増額され、その増額率は一生変わらない。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができる。
繰下げ請求を希望されるときに「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出。
- ■繰下げ加算額
- 繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算する。
ただし、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象にならない。
・増額率(最大84%※1)=0.7%×65歳到達月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
- ※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となる。
- ※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になる。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となる。
- ※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算する。
- ※繰下げによる加算額の詳細についてはこちらでご覧ください。
年金の繰下げ受給
- ■繰下げをする際の注意点
- 繰下げをする際は、以下の点にご注意されたい。
- 1.加給年金額や振替加算額は増額の対象にならない。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができない。
- 2.65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えない。増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われる。昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなる。
- 3.日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはならない。
- 4.65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができない。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができる。
- 5.66歳に達した日以後の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えない。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができる。
- 6.厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなるので、年金の支払元である基金等にご確認されたい。
- 7.このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合がある。
- 8.繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできない。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われる。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなる。
- ■基金加入者の方へ
- 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受給している方が、老齢厚生年金の支給の繰下げ請求を希望する場合は、基金等の年金も合わせて繰下げとなるので、年金の支給先である基金等にご連絡をされたい。
- ※企業年金連合会への問合せ 0570(02)2666 ※IP電話からは 03(5777)2666
- ■繰下げ請求を行わず、さかのぼって年金を受け取る場合
- 繰下げを希望し、65歳時点では年金の請求を行わなかった場合でも、実際の年金の請求時に繰下げ申出をせず、65歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することも可能である。
- ■本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度(特例的な繰下げみなし増額制度)
- 70歳に到達した日後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前の日時点で繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることとなる。
- 繰下げみなし増額制度は昭和27年4月2日以後に生まれた方、または平成29年4月1日以後に受給権が発生した方が対象となる。
- 繰下げみなし増額制度は80歳以後に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は適用されない。
- 過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響する場合がある。
- ■届書の提出先
- 提出先は近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に提出されたい。
- ■様式
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書
障害厚生年金の請求手続き
- ・障害厚生年金を受けられるとき
障害厚生年金を受けられるとき
- ■障害厚生年金の対象者
- 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給される。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給される。
- ※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要となる。
- (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
- ■請求書の提出について
- ●年金請求書
- 近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあるので、窓口に申出て受領されたい。
全国の相談・手続き窓口
- ●様式及び記入例
老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書
- ●年金請求に必要な書類
- 請求するときに必要な書類や添付書類等の詳細については下記にて確認されたい
請求するときに必要な書類等
- ●請求書の提出先
- 提出先は近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に提出されたい。
- 障害厚生年金の年金請求書提出までの流れについてはこちらをご覧ください。
年金請求書提出までの流れ
遺族厚生年金の請求手続き
- ■遺族厚生年金の対象者
- 遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる。
- ■請求するときに必要な書類等
- ●年金請求書
- 近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあるので、窓口に申出て受領されたい。
- ●様式及び記入例
- 遺族厚生年金の様式及び記入例の詳細についてはこちらをご覧ください。
遺族年金を請求するとき
- ●年金請求に必要な書類
- 遺族厚生年金の添付書類等の詳細についてはこちらをご覧ください。
遺族年金を受けられるとき
- ●請求書の提出先
- 提出先は近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出する。
外国籍の人が自国へ帰国し、脱退一時金を受給するときの手続き
- ■脱退一時金の請求先
- ●国民年金・厚生年金保険の期間のみである方の請求先
- 国民年金・厚生年金保険の期間のみである方の脱退一時金は、日本年金機構あてに請求手続きを行う。
- ●共済組合等の期間を有する方の請求先
- 共済組合等の期間を有する方の脱退一時金は、国民年金・厚生年金保険・共済組合等の加入期間を合算して、ひとつの実施機関が取りまとめて支給する仕組みとなっている。
- 1.国民年金の保険料納付済期間等が6月未満で、国民年金の脱退一時金が支給されない場合には、最後に加入していた被用者年金の実施機関(日本年金機構または各共済組合等)で取りまとめて支給するので、
・最後の加入が厚生年金保険(共済組合等以外)の場合は日本年金機構(例1)
・最後の加入が共済組合の場合は各共済組合等(例2)
あてに請求手続きを行う。
- 2.国民年金の保険料納付済期間等が6月以上あり、国民年金の脱退一時金が支給される場合には、日本年金機構が取りまとめて支給するので、日本年金機構あてに請求手続きを行う。(例3)
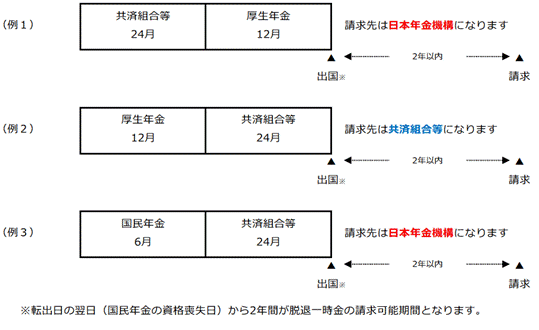
- ●脱退一時金の対象者
- 厚生年金保険の脱退一時金の支給要件は次のとおりとなっている。
- ・日本国籍を有していない
- ・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- ・厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
- ・老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
- ・障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
- ・日本国内に住所を有していない
- ・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
- ●脱退一時金を請求する方の手続きや添付書類等の詳細についてはこちらをご覧ください。
脱退一時金を請求する方の手続き